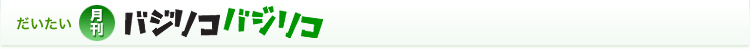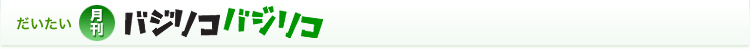雨だというのに、東京・渋谷にある映画館には大勢の若い男女が詰めかけていた。
その日、ある団体の主催するフィルムフェスティバルが開催されており、いくつもの作品が立てつづけに上映されていたのだ。
正午過ぎからは『ねこのひげ』という映画が上映され、終了後に監督や出演者による舞台挨拶が行なわれることになっていた。
開演ブザーが鳴り、会場内は暗くなる。二百ほどの客席はほぼ満席。
映画は、静寂のうちに幕を開け、奇を衒うことない物語は進んでいき、少しずつ少しずつ客席に染み渡っていく。
妻と幼い女の子を置き、別の女性のもとへ走った中年のシナリオライター。もう若くはないのだが、三年経っても籍を入れられずにいる。もどかしさを感じつつも、ともに暮らしつづける女性。周囲でも、さまざまな家族や恋人の関係が垣間見える。
ところどころでくすりという笑いが起きるほか、大きな葛藤も揺らぎもみられない。東京の私鉄沿線の商店街を舞台に、不安定な関係を続ける男女の日常が、淡々と、ときに訥々と綴られていく。
映画は、はじまりと同様、静かに幕を閉じた。
会場が明るくなると、矢城潤一監督、テレビでおなじみの藤田朋子、根岸季衣、ますます父親川谷拓三そっくりになってきた仁科貴らが壇上に登場した。主人公の「吉本えり」役の渡辺真起子は都合により顔を見せなかった。
そして、もう一方の主役を演じた大城(おおき)英司が現れると、一段と強い拍手が送られた。
大城が照れつつ、緊張した笑みを浮かべて監督の脇の椅子に座る。
スクリーンの向こうで見せていた表情である。
とくに二枚目でもなければ、一度見たら忘れられない異形でもない。普通の、どこにでもいる青年、いや、中年である。実年齢の四十歳よりは、多少は若く見えるか。壇上の顔ぶれのなかでは、最も名前と顔を知られていない俳優だろう。一般的には無名だと言ってもいい。きっと、彼が開場時に、受付でもぎりをやっていたことに気づいた客はいなかったはずだ。笑顔をふりまきながら、チケットを切っていたことに。
もちろん、理由もなく、もぎりをしていたわけではない。
実は、『ねこのひげ』は大城じしんが脚本を書き、実質的な制作者でもあるのだ。大城の想いを種子として、大城じしんが手をかけ育て上げた作品なのである。舞台挨拶には顔を見せていない、たとえば中原丈雄、馬渕晴子、蛍雪次郎、モロ師岡、川上麻衣子といった俳優たちも大城が声をかけて出演してもらった。ほとんどがノーギャラでの出演であった。
壇上では、一年前に終わった撮影時の苦労話や微笑ましいエピソードが語られていく。
大城も口を開き、ぼそっと説明を加える。
「主人公の暮らすマンションは、実際の僕の部屋でして、出演している猫もうちの飼い猫なんです」
あたかも「私小説」を読むがごとき印象を受けたのは、そのせいだったのか。作品の静けさと、ゆったりと沈み込むようなトーンは、そのまま大城の暮らし方に重なってくるのかもしれない。
*
早朝六時。大城は目を覚ますと、その日の行動に思いを馳せる。
今日の「現場」はどこで、どのような作業になるのか。
食事をとり、午前七時半までに「現場」に到着できるように自宅を出る。たいていは自家用車かバイクを使う。「現場」によっては電車を使うこともある。
「現場」は、たいていが駅だ。それは、私鉄の駅のこともあればJRの駅のこともある。
八時からはラジオ体操が行なわれ、その後に朝礼がある。それまでには着替えておかねばならない。
「現場」に着くと、大城は仲間のいる休憩室へと赴き、バッグから作業着を取り出す。
上着を羽織り、ニッカーと呼ばれるズボンをはく。膝までが膨らんでおり、膝下から細くなった、いわゆるニッカーボッカーである。
「現場」に出ていき、仲間たちとともに整列する。ラジオ体操で体を動かしながら、いろいろな段取りが頭をよぎっていく。
今日は足場を組み、夕方には解体し、その足で別の「現場」へと向かわねばならない。
少しずつ「映画」や「俳優」といった言葉が頭から離れていく。
大城の、「鳶職」としての一日は、たとえば、こんなふうにしてはじまっていく。
大城が鳶の仕事をはじめたのは、十年ほど前、三十歳になったころである。
すでに結婚もしていて、妻はスチュワーデスの仕事もしていたのだが、妊娠のための休職期間にあたっていた。
そんなとき先輩俳優に紹介されて、浅草の町鳶の親方の元で働かせてもらうことになったのだ。
鳶というのは、もともとは江戸の火消したちが傍らに従事していた仕事が、やがて消防署ができたことで、本業となっていったものである。材木などに引っかける鳶口という道具を使うため鳶と呼ばれたそうだが、真偽は明らかではない。この流れに位置する鳶職を町鳶と呼ぶ。
仕事の内容は、建築現場の足場を組むこと、そこに道具を運ぶことである。鳶が作業を終えたときから、現場での仕事がスタートするとも言える。だから、鳶というのは現場で一番偉いんだと、町鳶の人たちは教わったそうである。
一方、大手の建築会社などの現場を野丁場と呼ぶが、そうした大きな現場を専門にしている鳶職もいる。仕事の内容は同じであるが、こちらのほうが鉄骨なども扱うため規模は大きくなるし、仕事の内容も多岐にわたってくる。
大城は初めは町鳶の親方と二人で仕事に就いていた。俳優の仕事が入ると休んでいいという条件だった。ここで鳶の仕事の基本を教わり、その後、鉄道関係の現場を中心にしている会社に誘われ、働かせてもらうことになる。
駅舎の工事だから、日勤だけでなく、終電から始発までの間の作業があり、それは夜勤業務となる。四時間程度の作業だから、日勤と夜勤とをかけもちすることもできる。
大城は可能な限り、かけもちするようにしている。
夕方四時半ごろ、日勤の仕事を終えると、一度家に戻る。夕飯を食べ、早ければ七時には仮眠をとる。十一時ごろに起きて十二時半までに現場へ。朝礼ならぬ夕礼に間に合うように向かう。この時間だと、ほとんどが車かバイクでの通勤になる。
そして翌日の四時に作業が終了。日勤も同じ現場のときは、家に帰らずそこの休憩所で眠る。別の現場だと、家に戻り、再び仮眠をとる。
こうした状態が連日つづくことは少ない。たいていは、間が空いて、再び日勤、夜勤となるのだ。ただ、突貫工事で連日連夜、この昼夜勤務がつづくこともある。かつて、JRの大崎駅の現場では、月に二十五日間、日勤と夜勤をかけもちした。労働日数は、日勤でも夜勤でも一日に算定されるので、この月は五十日間働いたことになる。
「僕は、お金のために仕事をしていると割り切っているので、一切文句は言わないんです。次に、どこそこの現場に行ってくれと言われれば、素直に従います。日勤と夜勤とが離れたところにあっても、まったく気にならない。だって、それも含めて仕事なわけですからね」
その代わり、俳優の仕事があれば、あくまでそちらを優先させてもらう。
たとえば、二〇〇六(平成十八)年の七月から九月にかけて、大城は東海テレビ制作の昼ドラマ『美しい罠』に出演していた。
カトリーヌ・アルレーの『わらの女』を翻案したもので、主演は桜井淳子。大城はヒロインを狙う乗っ取り屋で、クセのある悪役といったところか。
こうした昼の連続ドラマの場合、火曜日がリハーサル、水曜日から日曜までがスタジオで撮影。月曜日がロケとなっている。
リハーサルも本番も出番のある日の、その時間に向かえばいいので、スケジュールが組みやすい。自分の出番の際は鳶のほうは休むことになる。
本番の日は、朝、出がけにシャワー浴びる。夏ならば短パンにTシャツ、冬ならジャージ、髪の毛は洗いざらしのままで出かける。どうせ、メイクをしてもらい、着替えねばならないから。
「実は、あの映画を撮り終えた後、事務所を辞めましてね。いまはフリーなんです。営業に回ったりしないから、知り合いが声をかけてくれる仕事がほとんどです。事務所に入っていると、だいたいギャラの三割は引かれるので七割しかもらえない。フリーだと、まるまる入るけど、営業も自分でやらないといけないから、どっちが良いかは簡単に言えませんね」
そして、ドラマが終わったいま、再び駅の現場へと通いはじめている。 |
|