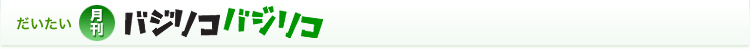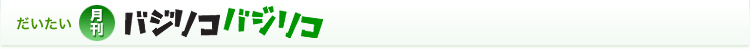「現実でも一人。ネットでも一人」という秋葉原通り魔殺人事件の犯人の書き込みは悲痛だ。どこにも自分の「居場所」というものがない。
自分の居場所というのは、誰にも干渉されない自分だけの部屋に閉じこもることではない。また知り合いばかりが居る空間がそうであるともいえない。知ってる人ばかりのなあなあ集団は確かに楽かもしれないが、その内部ではだれもが親密ではないのは言わずもがなだ。
この事件の現場である秋葉原というところは、今の東京ならではの街である。パソコン関連の専門店、フィギュアやアニメやメイドカフェ、歩いている若者はイヤホンをしているか下を向いているかで、他や外に対しての意識や身体感度を極力落としている。さもなければ同じネタだけでつながっているおたく的な友だち同士である。今の東京ならではと書いたが、こういう場所は他所にはないし、大阪では同様の街として「日本橋筋」があげられるが、そこはまだまだ「電化製品の街」という手触りが強い。同じ殺人事件がこの日本橋筋で起こっているが、それは地元の暴力団の大日本正義団会長・吉田芳弘が電器店で買い物後に山口組系の組員に射殺されたものだ。所謂「大阪戦争」の暴力団抗争事件の一つとして記憶にとどめている。
秋葉原というところは、顔がない「一人ぼっちのみんな」でいっぱいの街だ。その「一人ぼっちのみんな」は原宿の「オレたち」や新宿歌舞伎町の「あの人たち」的ではない、のっぺりとした「みんな」を形成している。その「みんな」はもちろん「知らない人」ばかりの集団だ。
街で「知らない人なのに知っている人」に出会うこと。そういう機会がまだまだ多いのが大阪という街の特徴であり、そういうところをわたしたちは多分に感覚的な言い方で「街場」などと呼んだりしている。秋葉原はそういう「街場」な感じがしない。加えてものすごく多くの人が行き交うこの街には「一人ぼっち」の「みんな」が何かにシンクロしているような気配がして、その何かが不気味である。
「知らない人なのに知っている人」というのは、その人の名前やその人の属性、どこで何をやっている人なのかは「知らない」けれど「知っている人」のことである。逆にどこで何をしているのかを「知っている人」なのに「知らない人」というパターンもある。これは「顔見知り」の関係性みたいなもので、なかなか微妙である。といっても当然、見知らぬ街や初めて入った店では見知らぬ人ばかりだから、「顔見知り」というのは自分にとっての地元感覚のある街やよく行く店での関係性である。
しかしながら旅行や用事でよその街に行って、お腹がすいたと店の外観をさんざん観察した末に飲食店に入ったりあれこれ嗅ぎ回りながら酒場の扉を開けてカウンターに座った時、その「場所」を占めている人々がそういった顔見知り関係である気配を感じたときに、完全にエトランゼであるはずの「わたし」がそこに自分の「居場所」を見つけたりすることが多い。それはその瞬間にここという場所がその人たちの何ものでもない居場所であるということがわかるからだ。その時、わたしはすでに「知らない人なのに知っている人」に出会っている。だから知らないとこの知らない人に会釈をしたりする。その人たちには「わたし」は悪意や敵意を持つことはないし、その人たちもわたしを少しばかり受け入れてくれる。場合によってはコミュニケーションも始まる。
見知らぬ国の見知らぬ街を歩き回り、見知らぬ人に囲まれて、ふと自分の居場所を見つけたりすることは、何ものでもない旅行のかけがえのなさや楽しさでもある。旅というのはそういった知らない場所で自分の居場所を見つけるプロセスそのものだし、まるで「今−ここ」を旅することに、自分のパーソナルヒストリーがすべて関わっているような気がする。
わたしは長いことマスターがサイホンでコーヒーを入れてくれる喫茶店やメニューにうどんと丼や寿司がある食堂やおばちゃんが注文を聞いて焼いてくれるお好み焼き屋といった街で育った関係か、ずらりと横並びで食べるファーストフードの牛丼屋や「スモール、トール、グランデとありますが」とレジで聞かれて注文し、違うカウンターで受け取り席をさがすタイプのカフェはつらい。そこに「居場所」というものを感じたりすることはほとんどないからだ。
「知らない人なのに知っている人」が少なからずいるということは、そういう〈郊外化〉された場所では顕在化しない。コンビニやファミレスでは「あそこはオレの行きつけの店だから、今度マスターに紹介してやるよ」といった「顔見知り」関係が出来ないようになっている。人と人とが出会わなくても経済が回るシステムであり、そこでは店のスタッフも客も代替可能である。そういうところに「居場所」を見つけることは難しい。
「社会」というものはまさにその「場所」においてのコミュニケーションのありようであり「社会はコミュニケーションからなり、あらゆるコミュニケーションは社会において生じる。従って社会は複数の人間の集合体として成立するのではない。人間は社会システムの構成要素でなく、その環境である。(馬場靖雄『ルーマンの社会理論』p.49)」ということである。
〈郊外化〉とは交換の原理に貫かれた均一大量のフラットな場所ばかりになることで、それはひたすら余計なコミュニケーションを省略して(スマイル0円)、経済を回していこうという「社会環境」であるから、そこには社会システムの「環境」であるところの「人間」というものは前に出てこない。〈システム〉だけがあり〈生活世界〉がない場所、そこには「居場所」どころか「社会」がないのかもしれない。
その〈郊外化〉という言い方は、都心/郊外のバイナリーコードをイメージしがちでなかなか微妙なものがあるが、宮台真司が踏み込んで次のように書いている。
「郊外化は二つのステップを経て進んだ。第一段階の郊外化は、主要には1960年代の──正確には50年代半ばから70年代末にかけての──プロセスで、「団地化」と呼べる。第二段階の郊外化は、主要には1980年代の──正確には80年代初頭から現在まで続く──プロセスで、「コンビニ&ファミレス化」と呼べる。(MIYADAI.com
Blog 2008-06-19)」
団地にしろファミレスにしろ〈郊外化〉された場所においての「知らない人なのに知っている人」の存在は、むしろ気持ちが悪い存在である。だからそこで会う人とはずっと知らないままである。
この「知らない人なのに知っている人」へのコミュニケーションを橋本治は『いま私たちが考えるべきこと』(新潮社)で「考えて」いる。
橋本さんは作家として駆け出しの頃、商店街の菓子屋をやっていた実家に住んでいたのだが、ある日編集者が家に迎えに来て、そこから駅に行くまでに30人を超える人に「こんにちはー」と挨拶をした。それを見た編集者は「なんでそんなに知ってるんですか?」と驚いたそうだ。
橋本さんの家は「気取ってる」と言われがちな東京の「山の手」で、別に「人情の厚い下町ではない」。その「こんにちはー」の相手は、「(よくは知らないが)よく会う、つまり知ってる人だけの人」で、そういう人は「敵意の持つ必要のない人」になり、そのことによって住環境はおだやかになるから、悪いことじゃない。「人と人に間にあるのりしろ」みたいなものだ、と鋭く書いている。その関係性は「地域社会が健全で健在だったから」で、それが「ムラ社会」か「マチ社会」かのどちらであるかは「マチ社会だってムラ社会みたいなもんだから、マチ社会とムラ社会のちがいなんかよく分からない」とも思っている。
とても「街的」な言及である。「知らない人なのに知っている人」が多いことは「街場」つまり「街的な場所」そのものだからだ。「知っている人」ばかりで構成されている社会は旧い「ムラ社会」で、「知らない人」ばかりの匿名的社会は「都会(都市社会)」であるという二項対立的な見方は、完全に「ムラ社会」からのもので、そういう観点からしか世の中を見られない人をわたしは「いなかもの」だと思っているが、この半世紀の「都会化」の行き着く果てがこの〈郊外化〉すなわち「団地化」と「コンビニ&ファミレス化」なのだとしたら、「街場」は絶滅していくばかりである。そして「居場所」というものがどんどん見つけられなくなる。
この事件についてもさまざまな人がインターネット社会に関連づけていろんなことを述べ書いているが、そうではなくてわたしはこういったリアル社会の過酷さこそが犯人を秋葉原での凶行に追い込んだのだと思う。
居場所がないというのはいつも「一人ぼっち」であるということであり、人はそういうときに街に出て裏路地横丁に入り込み、束の間の居場所を見つけようとした。しかし郊外化された街は、ずらずらと並んでカゴに投げ込んだものを精算する大型スーパーや、列をなす同じ機械の前に人が同じようにかぶりつくパチンコのように、「一人ぼっちのみんな」がただ集団で居るところである。秋葉原はそういう現代の場末なのかも知れない。 |
|