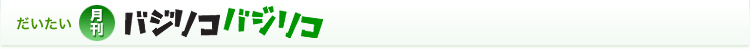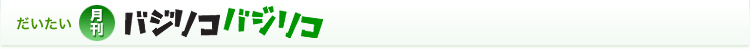「年にみえない」といわれることがほめ言葉になっている。人間はゆっくりと年輪をかさね、年を重ねるごとに、よい味が出てくる、もののはずだったが、「まあ、そのお年には見えませんね」というのが、何よりの賞賛となっている。「いい年のとり方をしていらっしゃいますね」とは、よほど気心が知れた人でなければいえない。
逆に、若いころは、年より上に見られるほうが誇らしかったりする。「あら、そんなに若いの。もっと大人に見えるわ」なんていわれるとうれしい。あるがままでいることはわたしたちは本当にいやなようだ。
わたしは40代も後半の教師だ。40代後半の教師らしい格好をしたい。40代後半の教師だから、40代後半の教師のように見えると安心する。今の私でないものに見てもらいたい、という希望はない。48歳の教師はどのように装うべきか。48歳相応の、教師という分相応の、私でいたい。教師に、派手な色や、色とりどりの花などは似合わないと思う。人の前に立ち、大勢を前に話をさせてもらい、個人個人の学生さんとむかいあう。前にいる人に、不安を与えることは、教育上好ましくない。学生さんには、いつも安心してもらいたいし、そのためには自分が着ていて安心で着るきものがなによりだ。結局、紺地をはじめとする濃い地色のおとなしいきものばかり着ている。実際に似合っているのか、年相応なのか、本当のところは、もちろんわからず、自信もないけれども。
きものを着るようになって、感じるようになった感情のひとつがこの「分相応」「年相応」である。分相応ということは大切だけれどもいまや死語にちかい。「新しいまだ知らないわたし」をもとめて、貪欲にガンガンキャリアアップしていくことがむしろ今の美徳なのであって、自分はこれだけのもの、と線をひいてしまう分相応、という言い方は、いかにも保守的なように思われてしまう。しかし、分相応を学ばないと、いつまでたってもささやかな幸せはない。駆り立てられて生きることは、本当はとてもつらい。
きものでは、分相応を学べる。洋服では学べない。誰だってお金さえあって、適度に細ければ、アルマーニやダナキャランを着ていいような気がしてしまうのはなぜだろう? その昔、東京で働き始めたころ最初のボーナスをはたいて、15万もするようなアクアスキュータムのブルーのコートを買ったことがあるのだが、そういうものを買って、小さなアパートの一室に住んでいることが分不相応である、と誰も言ってくれなかった。ところがきものを着始めると、この「分相応」がなんだかじわじわと利いてくる。
わたしは一介の教師で、親に金があるわけでなく、玉の輿に乗っているわけでもない。育ち盛りの息子も2人いる。こういう人間は、贅沢などしてはいけないのだと思い知る。もくもくと、営々と日々の生活にはげみ、地味な研鑽をしていくべきなのである。金糸銀糸の贅沢なきものなど絶対に買ってはいけない。きものを着たいのなら、地味な普段着をそろえ、毎日着るのがよい。訪問着や、付け下げや、といった贅沢品にはできるだけ手を出さないことだと思っている。
藍染のもめんの単衣や、紬、縞の小紋、夏の小千谷縮、といったものを着ているとおちつく。式やパーティーなどどうしても格式のある場に出なければならないときは、紋付の無地や江戸小紋に、袋帯を合わせるのが、一介の教師としては、一番安心していられる気が今はしている。目立たなくても、礼を尽くした格好であればよい。もちろんそのためには、しかるべききものに詳しい人のアドバイスが必要なことはいうまでもない。わたしのきものメンターのニドさんが、初めてきものを仕立てるときに、「まず、紫の無地にひとつ紋をつけて」といってくださったのは、いかにも分相応で、かつ礼を失することのない、的確なアドバイスだったと今も感謝している。紫の紋付の無地のきものは、入学式、卒業式にも、パーティーにも、不祝儀にさえも使うことのできるほんとうにありがたいきものだ。
きものの値段は文字通りぴんからきりまである。きものほど値段に幅があるものはない。あっという間に一桁違う、ということになる。きものは高い。確かに高い。しかしお金がないのならば、「高いきもの」には手を出さないことである。借金しなければ買えないようなきものを買うことが分不相応なのだ。買える範囲で、買えるきものを買う。将来において、お金ができたら、買えばよい。できなければ、それなりに、分相応に暮らす。今はリサイクルのきものもとてもよいものが出回っており1万円から2万円で気に入ったものをみつけることもできるだろう。そうやって、慣れて、お金をためて、すこしずつ買い揃えればよい。
ただ、きものを着始めると、きものに狂う。「お金があればきものが買いたい」病にかかる。とくに、着始めて最初の半年くらいは、みんな寝てもさめてもきもののことばかり考えている、という恐ろしい時期に見舞われる。時間さえあれば、リサイクルショップをのぞきたくなる。これはわたしたち日本をふるさととする人間のDNAに刷り込まれているのではないか、と思われるほど、きものを着始めた人間に共通だ。また、そういう時期には、きもののほうから集まってくる。なんだか、たくさんの方にきものをいただくのである。そうやってきものから逃れられなくなる。そして、こんな甘いわななら、分相応な範囲で、はまってしまってもよい、とあきらめてゆくのである。 |
|