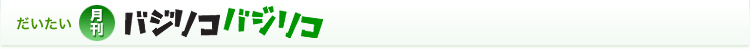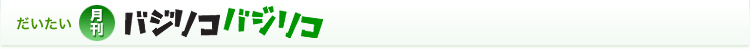久しぶりに暮らす故郷は、時間の流れがやけに緩やかに感じられた。
ちょうど、この実家に戻っている時、先に応募しておいた「オール讀物推理新人賞」の最終選考に鈴木の名前が連なる。
このときは、「もしかしたら、いけるか」と期待を抱いたが、受賞はならなかった。受賞者は、宮部みゆき。「相手が悪かった」といまでは諦めがついている。
本腰を入れて書いてみようか。そのためには就職しないで、このまま家業を手伝っていくのが良いのではないか。
社長である父に頼むと、鏝作りの工場で働かせてくれるという。槌を持って鉄板を叩いていって、鏝を作り上げる仕事だ。
幼いころから目にしてきた仕事である。門前の小僧ではないが、やってみると、すぐに覚えた。
一方、小説のほうは、我流で書いていてもこれ以上は伸びないかもしれないと思いはじめ、東京で行なわれていた小説教室に通うことにする。開講日である毎週土曜日は仕事を休ませてくれと父に頼むと、簡単に許してくれた。月給を日割り計算して、しっかり四日分を引かれたが。
こうして、鈴木さんの「鈴木コテ製作所」での仕事がはじまった。
「ゆるゆると、てれてれと、何となくはじめたところ、ずるずると今日に至るという感じですかね」
この小説教室に講師で来ていた大手出版社の編集者と話しているとき、「こんなネタがあるんですけど」と持ちかけたところ、「書いてみたら」と言われた。
急いで書き上げて、持っていくと、即座に出版が決まる。これがデビュー作『情断!』(講談社)であった。
「デビューしたと言っても、暇なもんでしたよ。三、四ヶ月で短編一本というぐらい。ですから、あのころはコテ屋の傍ら小説を書いているような状態でした」
一九九四年、「めんどうみてあげるね」で第四十七回推理作家協会賞(短編および連作短編集部門)を受賞する。
新宿職安前託老所とサブタイトルがつけられているが、いわゆるデイサービスの施設が舞台の「ちょっと怖い話」だ。
選考委員の作家、逢坂剛は《暗いテーマをあっけらかんと描いた奇妙な味》の作品と評し、同じく選考委員の日下圭介は《託老所という舞台設定も興味をそそられたし、人物も活きている》と好意的な選評を寄せていた。
これ以降、少しずつ、原稿の依頼が増えて、小説家の仕事のほうが主になっていった。
また、ジャンルもミステリーから時代小説、歴史小説と広がっていき、いまでは歴史小説のほうがよく知られるようになっている。
*
「父親と仲が悪かったんです」
なぜ、大学を出た後、すぐに実家に戻らなかったのかと尋ねたときだ。鈴木さんは、そう答えてくれた。
実はね、と教えてくれた。鈴木さんの父親は、彼が十歳のときから三十年間にわたって大垣市の市会議員をやっていたのだという。家には人の出入りも激しく、連日のように客たちに御馳走が振るまわれた。鈴木さんの記憶にある夕飯とは、煙草の匂いが染み込んだ助六寿司だったという。
父は六十八歳になったときに脳梗塞で倒れ、以後、立候補することは諦めるのだが、それまでは、いわば「窓際市会議員」のようなものだった。
その父親が亡くなるのが二〇〇二(平成十四)年のこと。
父の死と同時に鈴木さんが社長の座に就くことになる。
「とにかく社長になって分かったことは、社員は仕事や会社が嫌になったら辞められるけど、社長は辞められない、ってこと」
小説家一本で暮らしていこうと考えたことはないのだろうか。
「なくはないですけど、コテ屋の仕事も好きだから。それにね、大事なのは頭を下げる機会を持つことなんです。ほら、もともと尊大な性格だからさ、小説家だけやってると頭なんて下げないで済むでしょ」
父親が亡くなったとき、得意先への納品が大幅に遅れたことがあった。当主の死で家中ばたばたしてしまい、とても仕事のほうに頭が回らなかったのだ。
しかし、鏝を置く工務店にとっては、そんな事情は関係ない。
まず電話で、一方的に怒鳴られた。謝りにいくと、再び頭ごなしに怒声を浴びせかけられた。
非はこちらにある。言い訳したい気持ちを無理に納め、とにかく土下座をした。相手の予想を上回る謝り方でなければ、納得しないだろう。
鈴木さんが土下座して、ひたすら謝ると、相手の気持ちも落ち着いてくる。そのときになって、初めて「実は……」と父の死について説明したのだった。
「以前、よく言ってたのは、うちはコテと名のつくものは何でも扱いますよ。扱わないのは剣道のコテぐらい、ってね」
お好み焼き屋さんの小さなコテ、髪の毛にパーマを当てるためのコテだって、いざとなれば用意します。とにかく、そこまで間口を広げてナンボという商売なのである。
鏝屋と小説家、けっして主と従という関係ではないというが……何をやってもうまくいかず、一つでも取り柄が欲しいと考えてきて、やっと「少しは褒めてもらえた」のが小説家である。だから、「小説家として消えたくない」という思いは強く抱いている。
「あと、コテ屋をやってるメリットはね、実家で社長業やっていると言えば、食えなくて都落ちしたと思われなくて済むこと」
*
営業でいろいろな人たちと出会い、話をしていて、ふと気づいたことがある。工務店でも建具屋さんでも、いっとき傾きかけ、沈んでいた店が、ふっと生き返ったように元気を取り戻す瞬間があるのだという。その機会は二度あって、一度は跡取り息子が都会から戻ってきて家業を継いでくれたとき、もう一度は、そんな息子に赤ん坊が生まれたとき。
「どうしてかな、と考えて、やっぱり笑顔じゃないかと思ったの。この二度ばかりは、家中がニコニコ顔になっている。笑う門には福来たるって本当なんだと思いましたね」
てなことも、コテ屋じゃなきゃ経験できないじゃない、スズキさんはそう言って、楽しそうに笑う。
いつもセールスのときに着ているというジャンパーを羽織り、さっと立ち上がった。
どうもお世話になりましたと私が礼を告げると、「いえいえ、こちらこそ」と、まさに大黒様風の笑顔で答えてくれた。
これは、やはり鏝屋の笑顔なのだろうな。
|
|